細胞内に侵入した病原体を認識する新たな仕組みを発見
2025.04.07
研究
プレスリリース内容
発表のポイント
- 細胞の中に入り込んだ病原体を取り除く「オートファジー(注1)」が病原体を識別する際に、「HEATR3」という分子が目印として関与することを発見した。
- 「HEATR3」を介した仕組みは、これまで報告されているものと異なり、病原体の細胞質への侵入による細胞膜の損傷とそれに伴うカルシウムイオンの流出がきっかけであることがわかった。
- 全世界600万人以上、国内でも4.4万人以上いる炎症性腸疾患「クローン病(注2)」(指定難病96)の一部の患者では、HEATR3遺伝子に変異が見つかっており、本研究の発見は未だ明らかにされていないクローン病の病態発症の機構解明につながると期待される。
発表概要
私たちの体を構成する細胞は、ウイルスや細菌などの病原体が侵入した際に、それを排除しようとする防御機構を備えています。その一つに「オートファジー(注1)」という細胞内の自浄作用があり、特に病原体などの“異物”を分解するこのプロセスは「ゼノファジー」と呼ばれます。ゼノファジーが病原体を認識する仕組みとして、病原体そのものを認識する仕組みや、病原体に付加されたタンパク質を認識する仕組みなど、さまざまな仕組みがこれまで報告されていますが、その全容は未だ理解されていません。弘前大学 農188体育官网-【体育娱乐】@命科学部 細胞分子生物学分野 荒川将志 博士研究員(当時)、瓜生慧也 大学院生 (当時)、森田英嗣 教授らの研究グループは、産業技術総合研究所および大阪大学と共同で、炎症性腸疾患クローン病患者で遺伝子変異が見つかっている「HEATR3」というタンパク質がゼノファジーを制御する機能を担っていることを発見しました。また、「HEATR3」を介した病原体排除の仕組みは、これまで報告されているものと異なり、病原体が細胞の中に入り込んだ時に起こるエンドソーム(注3)膜の損傷とそれに伴うカルシウムイオンの流出がきっかけであることを明らかにしました。
本研究成果は2025年4月3日、世界で最も引用の多い総合科学誌のひとつである、米国科学アカデミー紀要「Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)」(インパクトファクター11.1)にオンライン版で公表されました。
発表内容
オートファジーに関連するタンパク質「HEATR3」の同定
ゼノファジー(オートファジーによる細菌などの病原体排除機構)が病原体を認識する仕組みを理解するために、まずオートファジーに関連するタンパク質を網羅的に探索しました。オートファジーが“異物”を認識する際に重要な役割を担うのが「オートファジー受容体」と呼ばれるタンパク質です。「オートファジー受容体」は“異物”に集積するとともに、オートファゴソーム膜(注4)上に存在する「LC3」というタンパク質に結合する性質を持ちます。さらに、そのLC3との結合にはLC3相互作用領域(LC3 interacting region, LIR)が重要と考えられています。そこで私たちは、ヒトの細胞内に存在するタンパク質の中からLIR依存的にLC3と結合するタンパク質を網羅的に探索し、Sec62、SQSTM1、TBC1D15など、すでにLIR依存的にLC3に結合することが報告されているタンパク質とともに、「HEATR3」などこれまでに報告の無いタンパク質を複数同定しました(図1)。

図1:LIR依存的にLC3に結合するタンパク質の探索
質量分析を用いて、LIR依存的にLC3に結合するタンパク質を網羅的に同定した。縦軸は値が低いほど、LIRへの依存性が高いことを意味する。 点一つが同定されたタンパク質を示す。
HEATR3の役割と細菌感染への関与
「HEATR3」はクローン病(注2)(細菌感染などにより腸に炎症が起こる難病)患者に変異がある遺伝子として知られていました。そこで私たちはHEATR3と細菌感染、そしてオートファジーとの関係に着目しました。詳細な顕微鏡観察の結果、細胞内に侵入した細菌にHEATR3が集まることが分かりました(図2A)。また、ゲノム編集技術を用いて、人為的にHEATR3遺伝子を欠損させると、感染細胞内での細菌の増殖が促進されることを明らかにしました(図2B)。さらに、欠損させたHEATR3を再発現させることでHEATR3の機能を回復させる実験では、LC3と結合できる正常なHEATR3の再発現では機能の回復が見られましたが、結合できない変異型では回復しませんでした(図2B)。これにより、LC3との相互作用がHEATR3を介した細菌の排除に不可欠であることが示されました。

図2:LC3の結合がHEATR3による細菌増殖制御に重要である
(A) HEATR3を発現させた細胞にサルモネラ菌を感染させた際の顕微鏡写真。緑はYFPを発現するサルモネラ菌、マゼンタはHEATR3を示す。
(B)サルモネラ菌の増殖試験。グラフは値が大きいほど、サルモネラ菌の増殖率が高いことを示す。HEATR3 KOはHEATR3遺伝子欠損細胞。HEATR3 KO +WTは野生型HEATR3を、HEATR3 KO +LIR2AはLC3に結合できないHEATR3変異体を、HEATR3欠損細胞にそれぞれ再発現させた細胞。グラフ上部にDunnett 検定(両側検定)による統計テストの結果(**; P < 0.01)を示している。NSは統計的有意差無しを示す。
HEATR3を介した病原体認識の仕組み
次に、HEATR3がどのようにして、細胞内に侵入した細菌に集まっているのか、その仕組みを解明するために種々の実験を進めました。さまざまな実験的検証から、HEATR3は細菌だけでなく“異物”の侵入によって損傷を受けた細胞膜(エンドソーム(注3)膜)や、化学処理によって損傷したリソソーム(注5)にも集積することが分かりました。また、それはオートファジー非依存的であること、膜損傷を受けたエンドソームやリソソームからのカルシウムイオンの流出に依存することがわかりました(図3)。これにより、HEATR3が損傷した細胞膜を感知し、異物を排除する役割を担っていると考えられます。

図3: HEATR3はカルシウムイオンの流出がきっかけで損傷膜に集積する。
HEATR3およびガレクチン3(Gal3、損傷膜を示す)を発現させた細胞にリソソームの膜損傷を引き起こす化学物質(LLOMe)とカルシウムイオンのキレート剤(BAPTA)を共処理した細胞の顕微鏡写真。緑はYFPを融合したGal3、マゼンタはHEATR3を示す。右のグラフは値が大きいほど、HEATR3の損傷膜への集積率が高いことを示す。BAPTA – はBAPTA未処理、BAPTA + はBAPTAを処理した細胞。グラフ上部にStudentのt検定(両側検定)による統計テストの結果(**; P < 0.01)を示している。
HEATR3と免疫反応の関係
HEATR3はクローン病との関連が示唆されている遺伝子です。そこで、免疫システムの特に、炎症反応を引き起こすNOD2を介したNF-κBシグナル伝達経路について、HEATR3の関与とオートファジーとの関連を検証しました。その結果、HEATR3はNF-κBシグナル伝達経路を正に制御していることがわかりましたが、その活性にオートファジー(LC3との結合)は関与していませんでした。このことは、HEATR3がクローン病などの炎症性疾患と関与していることが示唆されるが、それはオートファジー受容体としての機能とは独立していることを意味しています。
今後の展望
本研究の成果により、HEATR3を介した病原体などの細胞内の“異物”認識の新たな仕組みが明らかになりました。今回の研究は、細胞がどのようにして細菌感染を感知し、排除するのかを理解する上で重要な知見を提供しました。HEATR3の機能をさらに詳しく調べることで、クローン病などの病原体の感染に起因する感染症?免疫疾患に対する治療戦略の開発につながる可能性があります。
発表者
弘前大学農188体育官网-【体育娱乐】@命科学部分子生命科学 細胞分子生物学分野
森田 英嗣(教授)
荒川 将志(研究当時:博士研究員、現:秋田大学医学系研究科 助教)
瓜生 慧也(研究当時:大学院生、現:東京大学医科学研究所 特任研究員)
斉藤 晃樹(大学院生)
論文情報
論文題目: HEATR3 recognizes membrane rupture and facilitates xenophagy in response to Salmonella invasion.
著者: Masashi Arakawa?, Keiya Uriu?, Koki Saito, Mai Hirose, Kaoru Katoh, Krisana Asano, Akio Nakane, Tatsuya Saitoh, Tamotsu Yoshimori, Eiji Morita*
(?Equal contribution; *Corresponding author)
DOI: 10.1073/pnas.2420544122
URL: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2420544122
用語説明
- (注1) オートファジー
オートファジーは、細胞が自らの不要な成分や損傷した部分を分解し、再利用する過程を指します。このメカニズムは細胞の健康を維持するために非常に重要で、エネルギーの供給や新陳代謝、さらには病気の予防にも関与しています。 - (注2) クローン病
クローン病は、消化管(主に小腸や大腸)に炎症を引き起こす慢性の疾患で、免疫系の異常が原因とされています。発症には、遺伝的要因と環境要因が複雑に関与していると考えられていますが、いまだ明確には示されていません。食物の消化や栄養の吸収に関連する部分が炎症を起こすため、腹痛、下痢、体重減少、発熱などの症状が現れます。国内には4.4万人以上の患者が報告されており、厚生労働大臣が定める原因不明で治療方法が確立していない疾病(指定難病)に指定されています。 - (注3) エンドソーム
エンドソームは、細胞が外部から取り込んだ物質を一時的に貯蔵?輸送する膜構造です。必要な物質は細胞内で再利用され、不要なものは分解されるため、細胞の物流拠点として重要な役割を果たします。 - (注4) オートファゴソーム
オートファジーを駆動する隔離膜。小胞体膜が起源とされており、二重のリン脂質膜が標的を取り囲むように伸長し形成されます。 - (注5) リソソーム
リソソームは、細胞内の不要な物質や老廃物を分解する「細胞のゴミ処理場」とも呼ばれる小器官です。内部には強力な分解酵素が含まれており、エンドソームなどを経由して運ばれた不要な物質を効率的に処理します。
詳細
プレスリリース本文は こちら?(901KB)
プレスリリースに関するお問合せ先
弘前大学農188体育官网-【体育娱乐】@命科学部
教授 森田英嗣
TEL:0172-39-3586
E-mail:moritaehirosaki-u.ac.jp
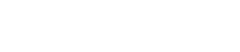


 背景色
背景色 文字サイズ
文字サイズ Language
Language